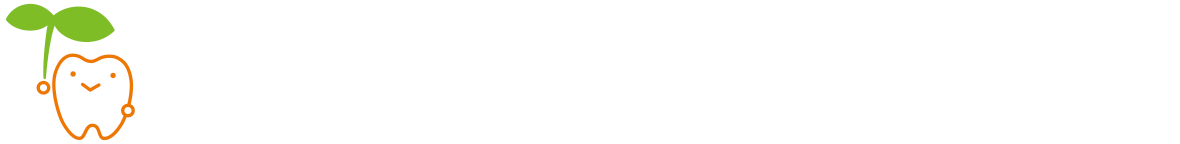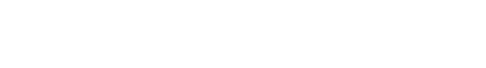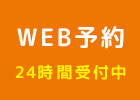歯並びが乱れた状態は、歯科の専門用語で「不正咬合(ふせいこうごう)」と呼ばれ、いくつかのタイプに分類されます。
この記事では、よく見られる不正咬合の種類について詳しく紹介します。
出っ歯、八重歯など、聞き慣れた言葉とあわせて、それぞれの名称や特徴についても解説します。
自分の歯並びのタイプを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
■不正咬合とは?
◎不正咬合とは何か
不正咬合とは、歯の噛み合わせが良くない状態のことを指します。
歯がデコボコしていたり、上下の歯が正しくかみ合わなかったりすることで、見た目だけでなく、咀嚼や発音、顎関節への負担となります。
放置しておくとむし歯や歯周病のリスクも高まり、将来的にトラブルを引き起こす可能性があります。
■叢生・ガタガタの歯並び
◎叢生(そうせい)とは
叢生とは、歯が重なり合って生えていたり、ねじれていたりする状態です。
いわゆるガタガタといわれる歯並びで、八重歯も叢生の一種に含まれます。
顎の大きさに対して歯の本数が多かったり、歯の生えるスペースが足りなかったりすることが原因です。
◎見た目や機能への影響
見た目のコンプレックスになりやすく、歯が重なり合っている箇所は歯磨きがしづらいため、むし歯や歯周病のリスクが高まります。また、咀嚼効率が下がることもあります。
■上顎前突・出っ歯
◎上顎前突(じょうがくぜんとつ)とは
上顎前突とは、上の前歯が前方に突出している状態を指します。
一般的に出っ歯と呼ばれる歯並びで、上の歯が下の歯より大きく前に出ているのが特徴です。
上顎が大きい、あるいは下顎が小さいなど骨格の問題や、幼少期の指しゃぶりや舌の癖が原因となることがあります。
◎見た目や健康への影響
唇が閉じにくくなったり、口が開きやすくなったりするため、口呼吸になりやすくなります。
乾燥しやすく、口臭や歯周病のリスクも上がります。
■下顎前突・受け口
◎下顎前突(かがくぜんとつ)とは
下顎前突とは、下の前歯や下顎が上の前歯より前に出ている状態です。
よく知られている名称として「受け口」とも呼ばれます。
下顎が過剰に成長していたり、上顎が未発達であったりすることが原因です。
◎見た目や健康への影響
見た目の印象が大きく変わるだけでなく、発音に影響することもあります。
咀嚼の効率も下がるため、食事の仕方にも支障が出ることがあります。
■開咬
◎開咬(かいこう)とは
開咬とは、奥歯が噛み合わせた際に、上下の前歯に隙間ができてしまう状態です。
幼少期の舌を出す癖や、指しゃぶり、口呼吸などが原因になることがあります。
◎機能面の問題
食べ物を前歯で噛み切ることが難しい場合があり、発音にも影響が出ることがあります。
特にサ行やタ行が不明瞭になることがあります。
■過蓋咬合・深すぎる噛み合わせ
◎過蓋咬合(かがいこうごう)とは
過蓋咬合は、噛み合わせが深すぎる状態で、上の前歯が下の前歯を覆いすぎてしまっている状態を指します。
下の歯がほとんど見えなくなるほど覆いかぶさっていることもあります。
◎注意すべき影響
顎に大きな負担がかかりやすく、顎関節症の原因となることもあります。
見た目のバランスも崩れるため、美容面で悩む方も少なくありません。
■空隙歯列・すきっ歯
◎空隙歯列(くうげきしれつ)とは
空隙歯列は、歯と歯の間にすき間がある状態です。
すきっ歯とも呼ばれます。生まれつき歯の本数が少なかったり、歯が小さかったりする場合に起こりやすくなります。
◎機能と見た目への影響
食べ物が詰まりやすく、発音にも影響することがあります。
特にサ行の発音が不明瞭になりやすく、人との会話で気にされる方も多いです。
■あなたの歯並びはどのタイプ?
◎自己判断は難しいこともある
ここまで紹介してきたように、不正咬合にはさまざまな種類があります。
見た目の問題だけでなく、口腔機能や全身の健康にも関係するため、気になる歯並びがある場合は歯科医院での診断を受けることが大切です。
【不正咬合は放置せず、早めの相談を】
不正咬合には叢生、上顎前突、下顎前突、開咬、過蓋咬合、空隙歯列など、さまざまな種類があります。
それぞれ原因や見た目、機能への影響が異なるため、自分の歯並びの状態を正しく知ることが第一歩となります。
歯並びの改善には、成長期を生かした矯正治療や成人矯正など、さまざまな選択肢があります。
気になる方は、まずは歯科医院で相談し、自分に合った対策を検討してみましょう。