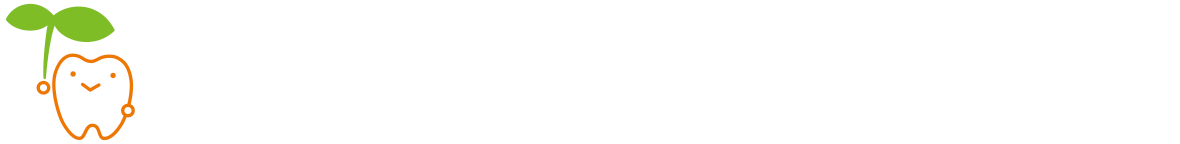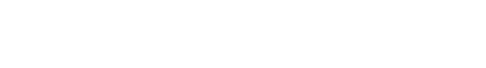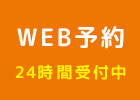インプラント治療は自費診療であり、比較的高額な費用がかかることが多いです。
しかし、医療費控除を使えば、確定申告によって一部の税金が控除、還付される可能性があります。
ここでは、インプラント治療が医療費控除の対象になる条件や申請の流れ、注意点についてわかりやすく解説します。
目次
■医療費控除とは?
◎所得税や住民税を軽減できる制度
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、所得から差し引くことができる制度です。
対象期間は一年単位で、1月1日から12月31日までで、確定申告によって還付を受ける形になります。
◎控除額の計算方法
控除額は「支払った医療費の総額」から「保険金などで補填された金額」と「10万円(所得が200万円未満の人は「10万円」ではなく「所得の5%」)」を差し引いた金額になります。
たとえば、医療費が70万円かかり、補填がなければ、60万円が控除対象となります。
これに所得に応じた税率を掛けます。
|
所得合計額 (課税される所得額) |
所得税率 |
控除額 (所得から差し引かれる控除額) |
|
195万円未満 |
5% |
0円 |
|
195万円超330万円未満 |
10% |
97,500円 |
|
330万円超695万円未満 |
20% |
427,500円 |
|
695万円超900万円未満 |
23% |
636,000円 |
|
900万円超1,800万円未満 |
33% |
1,536,000円 |
|
1,800万円超4,000万円未満 |
40% |
2,796,000円 |
|
4,000万円超 |
45% |
4,796,000円 |
■インプラント治療は医療費控除の対象になる?
◎治療目的であれば対象になる
インプラント治療は、咀嚼機能の回復や噛み合わせの改善など、医療目的で行われる場合には医療費控除の対象となります。
◎見た目だけを目的とする場合は対象外
審美目的で行う場合、たとえば単に美しく見せたいという理由でのインプラントは医療費控除の対象外です。
■控除の対象になる費用とは?
◎治療に関する費用一式
手術費や診察費、レントゲンやCTの撮影費、人工歯の製作費、麻酔代など、インプラント治療に直接かかわる費用は控除の対象となります。
骨造成などの前処置が必要な場合、その費用も含まれることがあります。
◎交通費も対象になる
通院にかかる交通費も条件によっては申告できます。
バスや電車など公共交通機関の利用が基本であり、タクシー代は特別な理由がない限り認められません。
■申請に必要な書類と注意点
◎領収書は保管が必要
平成30年以降、確定申告の際に領収書の提出は不要となりましたが、税務署から求められたときのために、5年間の保管が推奨されています。
◎医療費控除の明細書を提出する
確定申告時には、医療費控除の明細書を作成し、提出する必要があります。
誰が、いつ、どこで、どのような治療を受けたかを記録したこの書類を、あらかじめ用意しておきましょう。
■確定申告の時期と申請方法
◎申請は毎年2月16日から3月15日
医療費控除の申請は、治療を受けた翌年の2月中旬から3月中旬に行います。
この期間を過ぎると申告できない可能性があるため、スケジュールに注意しましょう。
◎e-Taxを使えば自宅から手続き可能
国税庁の電子申告システムであるe-Taxを利用すれば、自宅からオンラインで申告が可能です。
マイナンバーカードやICカードリーダーが必要ですが、還付金の処理も早く、窓口に行く手間も省けます。
■医療費控除を受けるメリット
◎大きな控除額となることも
インプラント治療は1本あたり30万円〜50万円程度の費用がかかることもあります。
複数本の治療や骨造成の処置が必要になった場合は、100万円を超えることも珍しくありません。
医療費控除を利用すれば、所得税や住民税が軽減され、実質的な負担が数万〜十数万円軽くなる可能性があります。
【医療費控除で経済的な負担を軽減しよう】
インプラント治療は費用面でハードルを感じやすいですが、医療費控除を受けることで、その負担を軽減できる可能性があります。
治療前から申告までの流れを把握しておけば、安心して治療に臨むことができるでしょう。わからないことがあれば、歯科医院や税務署に相談してみるのもおすすめです。
インプラントの費用が高い理由にについてはこちらもあわせてご覧ください。